 お葬式 お役立ち辞典
お葬式 お役立ち辞典
お通夜:流れとマナーとお悔やみの言葉、迷わないためのお通夜完全ガイド
大切な方を亡くされたご遺族にとって、お通夜は故人を偲び別れを告げる大切な儀式です。
しかし、お通夜に初めて参列する方にとっては、どのような流れで進行するのか、どのようなマナーがあるのか、不安に感じることも多いのではないでしょうか。
また、お悔やみの言葉を伝える際にも失礼のないようにしたいと考えるのは当然のことです。
この記事では、お通夜に初めて参列する方でも安心して臨めるよう、お通夜の流れ、マナー、そしてお悔やみの言葉を詳しく解説します。
宗教や宗派による違いにも触れながら知っておきたい情報を網羅していますので、ぜひ参考にしてください。
1.お通夜とは?
お通夜とは、大切な方を亡くされたご遺族、友人、知人などが集まり、故人を偲び、冥福を祈るための儀式です。
夜通し行われていたことから「通夜」と呼ばれていますが、近年では、1~3時間程度で終わる「半通夜」が一般的になっています。
お通夜の目的
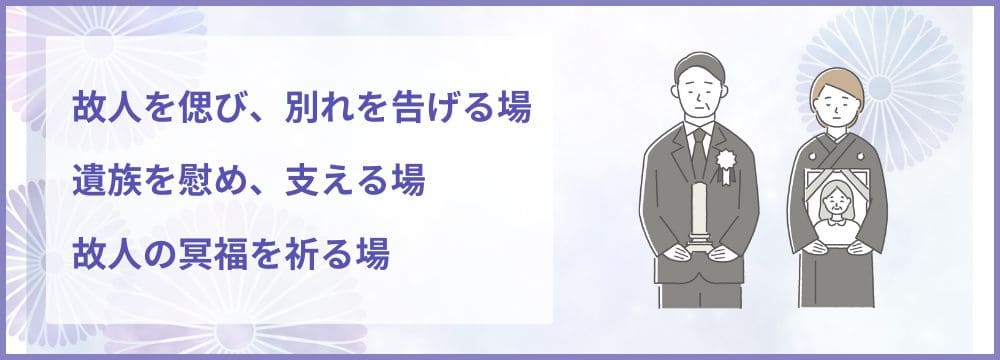
お通夜の主な目的は、以下の3つに集約されます。
・故人を偲び、別れを告げる場 : 親しい人々が集い、故人との思い出を語り合い、在りし日のお姿を偲びながら最後のお別れをする貴重な機会です。
・遺族を慰め、支える場 : 悲しみに打ちひしがれている遺族にとって、周囲の人々が寄り添い支えてくれることは、悲しみを分かち合えて心が和らぎます。
・故人の冥福を祈る場 : 故人の魂が安らかに眠りにつけるよう、読経や焼香などを通して祈りを捧げる場でもあります。
お通夜の持つ意味
お通夜は、単なる形式的な儀式ではなく、深い意味があります。
・心の整理をつける : 別れに直面した遺族は、悲しみや喪失感でいっぱいです。お通夜を通して、故人の死を受け止め、心の整理をつける時間を与えてくれます。
・故人との絆を再確認する : 故人との思い出を語り合うことで、故人との絆を再確認し、感謝の気持ちが深まります。
・コミュニティの結束を強める : 同士が集まって悲しみを共有することで、コミュニティの結束を強め、互いに支え合うことができます。
宗教・宗派による違い
お通夜の形式や内容は、宗教や宗派によって異なります。代表的な3つの宗教・宗派におけるお通夜の特徴を以下にまとめます。
仏式
僧侶による読経が行われ、参列者は焼香をして故人の冥福を祈ります。
一般的に、通夜振る舞いと呼ばれる食事が用意されます。
浄土真宗では、お通夜を「前夜式」と呼び、僧侶の読経はありません。
神式
神職による祭詞奏上(さいしそうじょう)が行われ、参列者は玉串を捧げて故人の平安を祈ります。
通夜祭とも呼ばれます。
キリスト教式
牧師による聖書の朗読や祈祷が行われます。
参列者は献花をして故人の平安を祈ります。
プロテスタントでは「前夜式」、カトリックでは「通夜祭」と呼ばれることもあります。
お通夜に参列する際は、事前に故人の宗教や宗派を確認し、適切な作法で参列することが大切です。
これらの情報を参考に、お通夜の意義と目的を理解し、故人を偲ぶ気持ちを持って参列しましょう。
2.お通夜の流れ

お通夜は、故人を偲ぶ気持ちとともに、失礼のないようマナーを守ることが大切です。 ここでは、お通夜の一般的な流れと、それぞれの場面での注意点について詳しく解説します。
受付
会場に到着したら、まずは受付を済ませます。
芳名帳への記帳
受付には芳名帳が用意されています。
自分の名前と住所を丁寧に記入しましょう。
夫婦で参列する場合は、夫婦連名で記入するのが一般的です。
香典の渡し方
香典は、受付で「ご霊前にお供えください」「お香典です」といった言葉とともに、袱紗(ふくさ)から取り出して両手で差し出します。
新札ではなく、旧札を用意するのがマナーです。新札は前以て準備していた印象があり、遺族が不快に思ってしまいかねないからです。
香典袋の水引は、仏式では黒白、神式では白銀、キリスト教式では白黒または双銀が主流です。
その他の注意点
受付で受付係に挨拶し、会葬御礼を受け取ります。
このタイミングでお悔やみの言葉を述べても構いませんが、混雑している場合は、焼香の際に遺族に直接伝えるようにしましょう。
焼香
受付を済ませたら焼香を行います。
焼香は、故人の冥福を祈るための儀式です。
焼香の作法
焼香の作法は宗派によって異なりますが、一般的には以下の手順で行います。
1.遺族に一礼する
2.焼香台の近くまで進み、遺影に一礼する
3.焼香台に進み、抹香(まっこう)をつまんで香炉にくべる
4.合掌し、心の中で故人を偲ぶ
5.遺族に一礼する
回数と作法
焼香の回数は、宗派によって異なります。
一般的には、仏式では1~3回、神式では2回、キリスト教式では1回とされています。
不安な場合は、周りの人に合わせて行うと良いでしょう。
その他の注意点
焼香の順番は、遺族、友人・知人の順に並ぶのが一般的です。
焼香の列に並ぶ際は、前の人の焼香が終わるまで、少し距離を置いて待ちましょう。
僧侶の読経(またはそれに準ずるもの)
焼香が終わると、僧侶による読経が行われます。この間は合掌し、静かに故人の冥福を祈りましょう。
神式では読経ではなく神職による祭詞奏上が、キリスト教式では牧師・神父による聖書の朗読や祈祷が行われます。
弔問客への挨拶
読経などが終わると、喪主や遺族が弔問客へ挨拶を行います。 この際、遺族に直接声をかけることは控えるのがマナーです。
通夜ぶるまい
仏式のお通夜では、通夜ぶるまいと呼ばれる簡単な食事が振る舞われることがあります。 通夜ぶるまいの席では、故人との思い出を語り合い、遺族を慰めることができます。
ただし、長居はせず、節度を守って食事を楽しみましょう。
通夜ぶるまいのマナー
・遺族が勧めるまで席に着かない
・乾杯の音頭は取らない
・宗教・宗派によっては、お酒を飲まない場合もある
・周囲の人との会話は、故人との思い出話や、遺族を気遣う言葉を選ぶ
・長居はせず、早めに失礼する
次章では、お通夜でのマナーについても確認していきましょう
3.お通夜でのマナー
お通夜に参列する際は失礼のないよう、服装や持ち物、香典など、基本的なマナーを押さえておきましょう。
服装
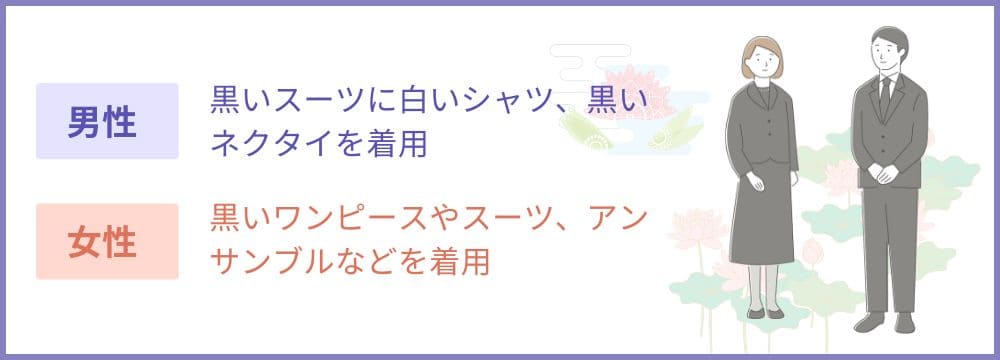
お通夜の服装は、基本的に喪服が基本です。
男性は、黒いスーツに白いシャツ、黒いネクタイを着用します。 女性は、黒いワンピースやスーツ、アンサンブルなどを着用します。 派手なアクセサリーやメイクは避け、地味な装いを心がけましょう。
関連記事:お葬式:お通夜/告別式に相応しい服装【迷わないための完全ガイド
持ち物
お通夜に持参するものは、以下の通りです。
・数珠 : 宗派によって形が異なりますが、仏式の葬儀には必ず持参しましょう。
・袱紗(ふくさ) : 香典を包むための布です。紫や緑など、地味な色を選びましょう。
・ハンカチ : 涙を拭いたり、手を清めたりする際に使用します。
・黒いバッグ : 小さめのハンドバッグや袱紗(ふくさ)が入るサイズのものが適切です。
関連記事:お葬式のマナー:バッグ選びで迷わないための完全ガイド
香典
香典は、故人の霊前に供える金銭です。
金額は、故人との関係性や地域によって異なりますが、一般的には友人・知人であれば5,000円~10,000円、職場関係であれば10,000円~30,000円、親族であれば30,000円~100,000円が相場とされています。
新札ではなく旧札を香典袋に入れ、袱紗(ふくさ)に包んで持参しましょう。
時間
お通夜は、開始時刻の10~15分前には到着するようにしましょう。 遅刻は厳禁です。
もし遅れてしまったら、受付で一言断りを入れてから静かに入場しましょう。
その他の注意点
・お悔やみの言葉は、短く、声を落として伝える : 遺族は悲しみに暮れているため、長話や大声での会話は避けましょう。
・故人の死因やプライベートな質問はしない : 遺族の気持ちを傷つける可能性があるため、デリケートな話題は避けましょう。
・お香典は、両手で差し出す : 袱紗(ふくさ)から取り出し、両手で丁寧に差し出しましょう。
・携帯電話の電源はオフにする : マナーモードではなく、必ず電源を切りましょう。
・通夜ぶるまいでの長居は避ける : 遺族や他の参列者に配慮し、節度を守って食事を楽しみましょう。
これらのマナーを守り、故人を偲ぶ気持ちを持ってお通夜に参列しましょう。
4.お通夜でのお悔やみの言葉
お通夜では、故人への弔意と遺族への気遣いを示すため、適切なお悔やみの言葉を伝えることが大切です。
受付での挨拶
受付では、まずお悔やみの言葉を述べましょう。
一般的な表現としては、
「この度は、まことにご愁傷さまでございます。」 「突然のことで、まだ信じられません。心よりお悔やみ申し上げます。」 「ご生前のご厚情に深く感謝いたします。」
などが挙げられます。
香典を渡す場合は、「ご霊前にお供えください」と一言添えて、両手で差し出しましょう。
焼香時
焼香の際には、声にせずとも心の中で故人を偲び、冥福を祈る気持ちを込めましょう。
遺族への言葉
遺族への言葉は、故人との関係性や親密度によって異なります。 親しい間柄であれば、
「○○さんのことは忘れません。」 「何か私にできることがあれば、遠慮なくお申し付けください。」 など、故人を偲ぶ言葉や、遺族を気遣う言葉を伝えることができます。
あまり親しくない間柄であれば、 「この度は、誠にご愁傷様です。」 「ご生前のご厚情に深く感謝いたします。」
など、形式的な言葉で十分です。
宗教・宗派別の注意点
宗教や宗派によって、避けるべき言葉や表現があります。
例えば、仏教では「ご冥福をお祈りいたします」という言葉が一般的ですが、神道とキリスト教では「ご冥福」という言葉は使いません。 「安らかにお眠りください」といった表現が適切です。
事前に故人の宗教や宗派を確認し、適切な言葉を選ぶようにしましょう。
また、宗派によっては、お悔やみの言葉の後に「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」や「アーメン」といった言葉を唱える場合があります。 不安な場合は周りの人に合わせて行動すると良いでしょう。
お悔やみの言葉は形式的なものではなく、心からの哀悼の意を伝えるものです。 故人を偲び、遺族の悲しみに寄り添う気持ちを込めて言葉を選びましょう。
5. まとめ
お通夜は、故人とのお別れを惜しみ、冥福を祈る大切な儀式です。
初めての参列は不安に思うことも多いかもしれませんが、この記事で紹介した流れやマナーを参考に、失礼のないよう心から故人を偲びましょう。
お悔やみの言葉は、形式的なものではなく、あなたの心からの気持ちを伝えることが大切です。
故人との関係性や状況に合わせて適切な言葉を選び、遺族の心に寄り添う気持ちを表しましょう。
この記事が、お通夜に参列する皆様のお役に立てれば幸いです。


























