 お葬式 お役立ち辞典
お葬式 お役立ち辞典
お悔みの言葉:葬儀後の遺族への声かけ、どうする?かけたい言葉・避ける言葉
お葬式の後、「遺族に声をかけたいのにどう言えばよいのかわからない……」と困っていませんか?あなたの言葉はきっとご遺族の心の支えになります。この記事では、状況に合わせたお悔みの言葉や気を付けたいことを、具体的な例を交えて紹介します。
1.葬儀後に遺族に言葉をかけるべき?
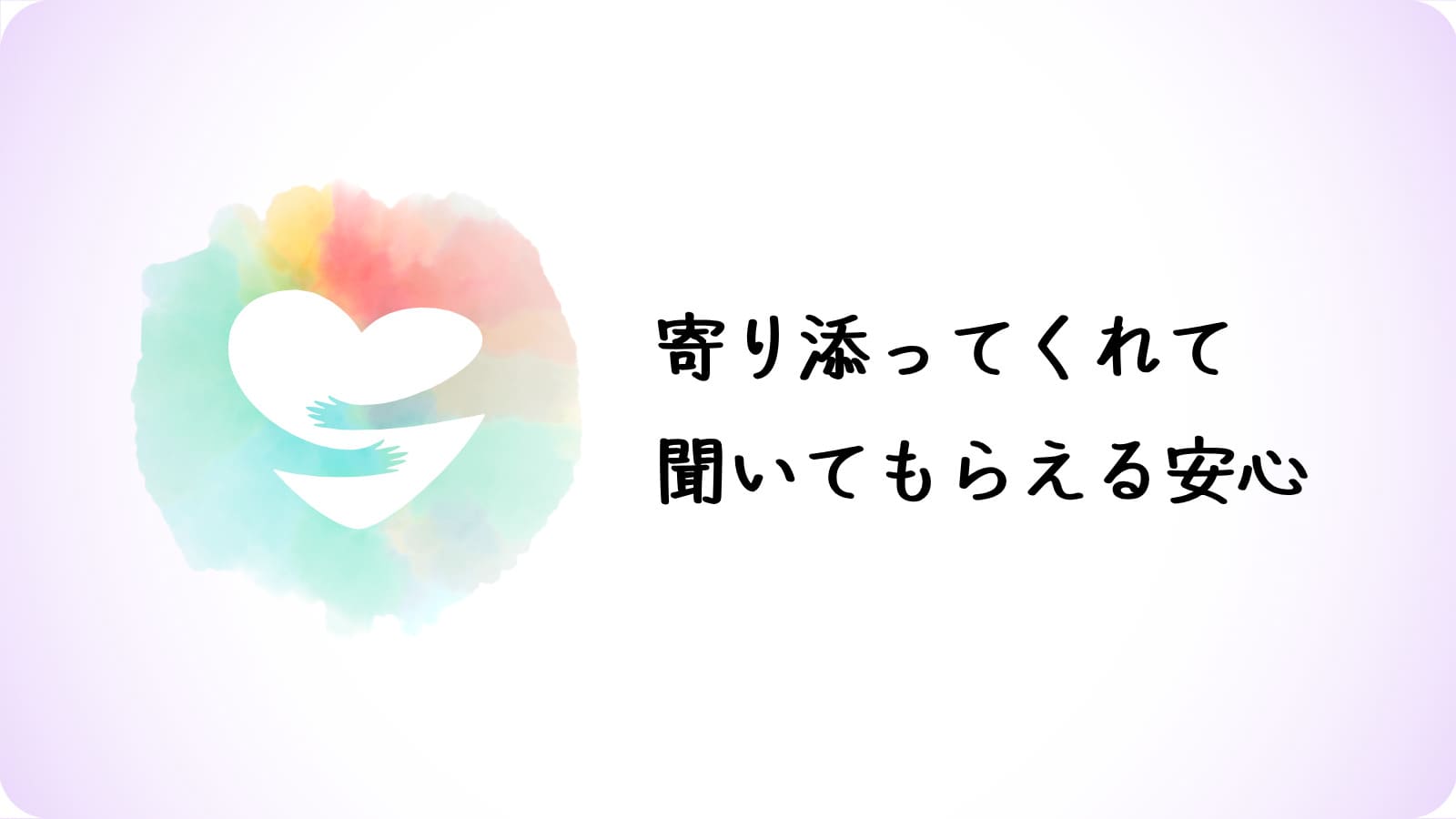
葬儀後の遺族の心理
葬儀を終えると、張り詰めていた緊張が緩み、悲しみや疲れがどっと押し寄せることがあります。また、周囲のサポートが減り、孤独を感じるかもしれません。そんな時に誰かが寄り添い、話を聞いてくれるだけで、心の負担が軽くなることがあります。
言葉をかける意味
葬儀後の遺族にかける言葉は、単なる形式的な挨拶ではありません。それは、
・遺族の悲しみに寄り添う気持ち
・故人を偲ぶ気持ち
・遺族を支えたいという気持ち
を伝えるためのものです。あなたの言葉は、遺族が悲しみを乗り越え、前を向くための小さな一歩を後押しするかもしれません。
言葉をかけるタイミング
葬儀後、ご遺族の方々が忙しくおられる場合、すぐに連絡をするのは避け、数日置いてから連絡を取りましょう。遺族は葬儀後の手続きや、気持ちの整理に時間を要することがあります。また、相手の様子を見ながら、落ち着いて話せるタイミングを見計らうことも大切です。
言葉をかける方法
直接会うのが難しい場合は、電話や手紙、メールでも構いません。ただし、SNSでのメッセージは避けましょう。また、相手が話しやすい雰囲気を作ることも大切です。
言葉をかける上での注意点
・故人の死因や病気について触れない
・「頑張って」「元気出して」など、励ますような言葉は避ける
・宗教や宗派に合わせた言葉を選ぶ
これらの点に注意し、遺族の気持ちを尊重しながら、温かい言葉をかけてあげましょう。詳しくは3章「遺族を傷つける言葉|避けるべき表現」で説明します。
葬儀後の遺族は、心身ともに疲れている状態です。あなたの言葉は、遺族の心を癒し、支える力となります。
「何か私にできることがあれば、遠慮なくお申し付けください」 「いつでもお話を聞きますよ」 このような言葉をかけることで、遺族は安心して、あなたに頼ることができるでしょう。 あなたの温かい言葉は、きっと遺族の心に届くはずです。
2.遺族にかけるべき言葉|温かい励ましのフレーズ集
葬儀の後も遺族は深い悲しみや喪失感の中にいます。そんな時にかけてもらえる言葉は、心の大きな支えとなるものです。でも「言いたいけれど言葉が見つからない」 「私の言葉でかえって傷ついてしまわないか心配」そう迷うのは自然なことです。
そこで、遺族に寄り添える言葉と伝え方をシーン別に紹介します。
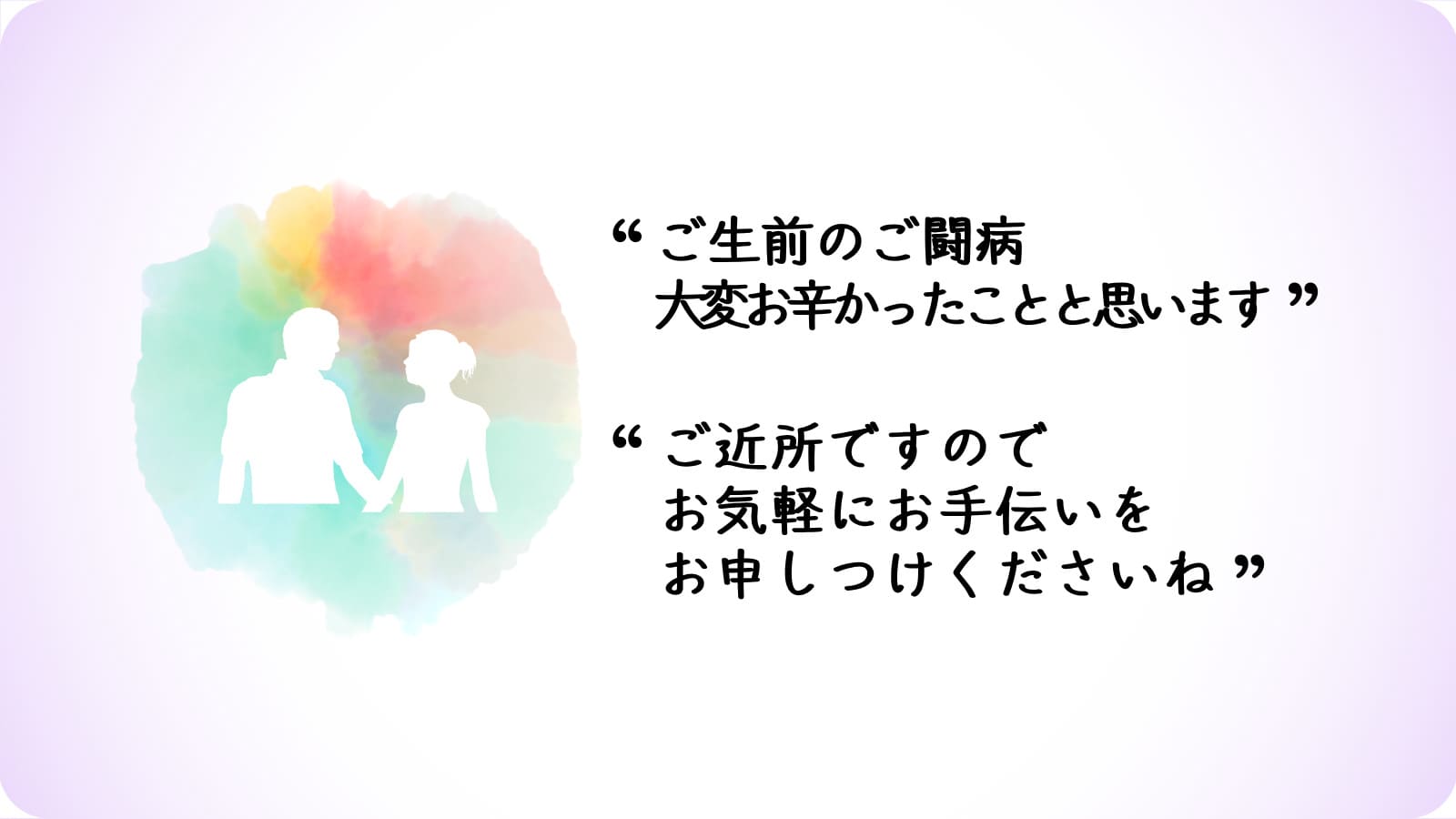
一般的なお悔やみの言葉
「この度は、まことにご愁傷様でございます。心からお悔やみ申し上げます。」
「この度は、思いがけないことでございました。さぞ、お力落としでございましょう。心からお悔やみ申し上げます。」
病気・事故・急死の場合
「ご生前のご闘病、大変お辛かったことと思います。心よりお悔やみ申し上げます。」
「突然のことで、お慰めの言葉もございません。ご遺族の悲しみいかばかりかとお察し申し上げます。」
「思いもかけないご災難に、言葉もありません。さぞ、おつらいことでございましょう。」
故人との関係性(お世話になった・近所)
「ご尊父様には、ひとかたならぬお世話をいただいておりましたのに、なんのご恩返しもできないままに、この度のご逝去。まことに心残りでございます。」
「この度は思いがけないことで、心よりお悔やみ申し上げます。もっとお元気でいていただきたかったのに、まことに残念でございます。」
「この度は突然のことで、心よりお悔やみ申し上げます。さぞ、おつらいことでございましょう。ご近所でございますので、なんなりとお気軽にお手伝いをお申しつけください。」
代理で弔問する場合
「この度は、まことにご愁傷様でございます。私は、お世話になっております鈴木太郎の妻光子でございます。本来ならば鈴木ともども駆けつけるべきところですが、あいにく鈴木は仕事で出張中のため、私が代わってお参りさせていただきました。鈴木は戻りしだいご焼香に参上させていただきます。本日の失礼をお許しくださいませ。」
故人と対面した場合
「安らかなお顔ですね。眠るような穏やかなお顔で、少し気が落ち着きました。」
どの宗教にも使える
「この度は、本当に思いがけないことでまことに残念でございます。」
「本当に残念なことで、心からお悔やみ申し上げます。」
お悔やみの言葉の後に添える言葉
「さぞ、お力落としでございましょう。どうぞ、お気をしっかりなさってください。」
「ご生前のご厚情に深く感謝いたしますとともに、心からご冥福をお祈りいたします。」
「何か私にできることがあれば、遠慮なくお申し付けください。」
3.遺族を傷つける言葉|避けるべき表現
遺族を励ましたい、慰めたいという気持ちで伝えた言葉でも、実は遺族を深く傷つけてしまう忌み言葉や、他の宗教用語かもしれません。そこで、葬儀後に避けるべき表現と、その理由について詳しく解説します。
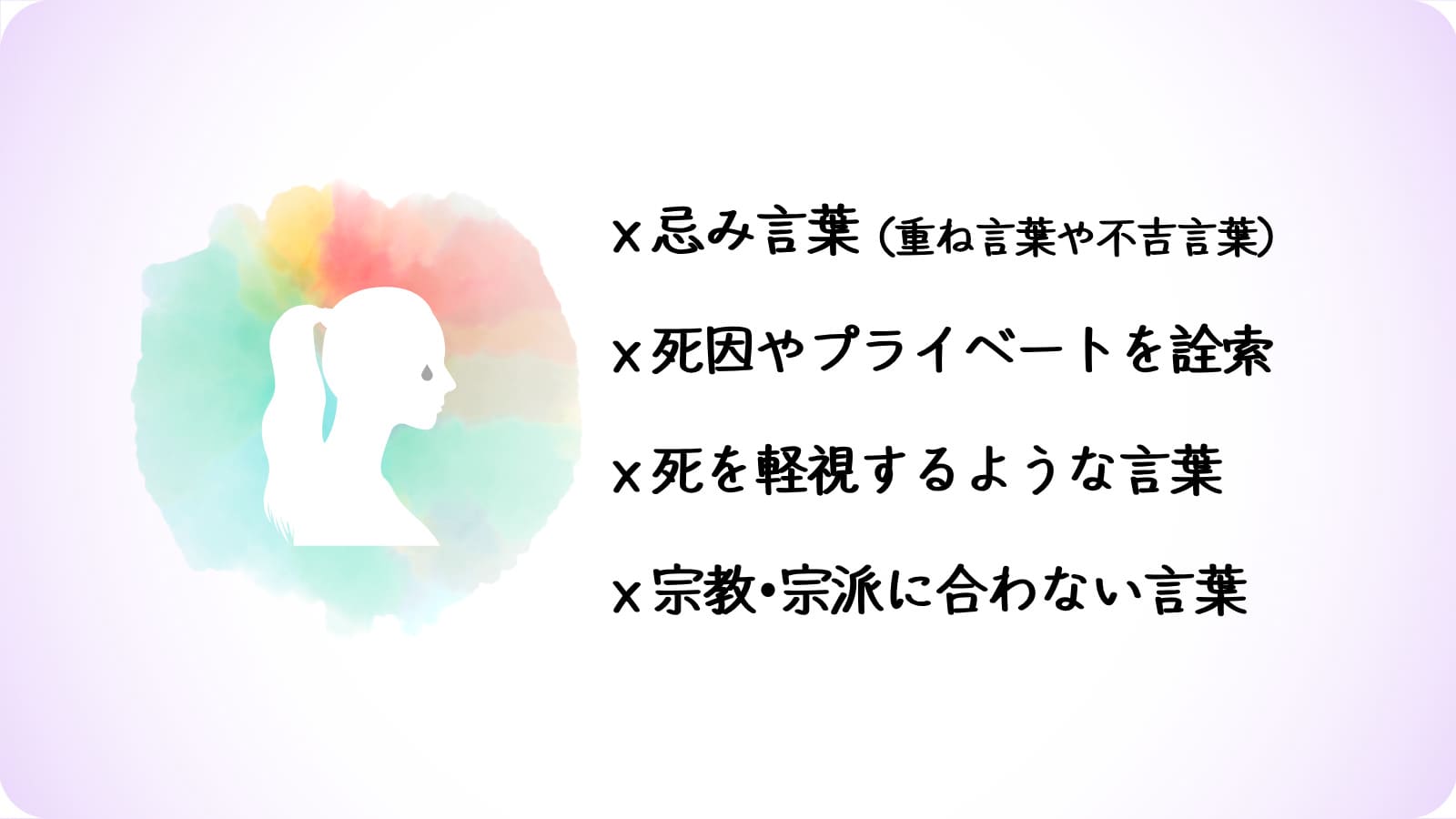
・忌み言葉 : 不幸を連想させる言葉です。重ね言葉や不吉言葉などあります。例)再び、追って、忙しい、4(死)、度々
・重ね言葉 : 同じ意味の言葉の繰り返しが、不幸の重なりを暗示させる言葉です。例)くれぐれも、度々
お悔やみの言葉を選ぶ際は、忌み言葉は避けます。再びは「改めて」、度々は「何度も」というように他の言葉に言い換えましょう。
故人の死因やプライベートに関する詮索
・「どうして亡くなったのですか?」
・「何か持病があったのですか?」
・「お仕事は何をされていたのですか?」
故人の死因やプライベートな情報は、遺族にとってデリケートなことです。事故などで突然訪れた死の場合は、より一層深い悲しみの中にいるでしょう。その悲しみをさらに深めぬよう、不用意な詮索はしません。
死を軽視するような言葉
・「まだお若いのに…」
・「お気の毒に…」
・「仕方ないですよ」
遺族の悲しみを軽視しているように聞こえ、不快な思いをさせてしまうことがあります。
再婚や子どものことなど、将来に関する話題
・「早く元気になって、新しい人生を歩んでくださいね」
・「お子さんのために、頑張ってください」
・「また良い人が見つかるといいですね」
将来のことはまだ考えられない状況です。特に、配偶者を亡くしたばかりの遺族にとっては、非常に辛い言葉となります。
宗教・宗派に合わない言葉
・「南無阿弥陀仏」(仏教の言葉です)
・「天国で安らかに」(キリスト教の言葉です)
宗教や宗派ごとに適切な言葉があります。
その他、避けるべき言葉
・「頑張ってください」
・「元気を出してください」
遺族にとってプレッシャーになりかねません。無理に励まそうとせず、寄り添う姿勢を示すことが大切です。
言葉選びのポイント
・故人の死を悼む言葉
・遺族の気持ちに寄り添う言葉
・宗教や宗派に配慮した言葉
・短く、シンプルな言葉
これらを踏まえ、遺族の心に寄り添う言葉をかけましょう。
でも、無理に言葉をかける必要はありません。言葉が見つからなければ静かに寄り添い、話を聞いてあげてください。これも心の大きな支えになるでしょう。
最も大切なことは、遺族の気持ちを尊重することです。相手の反応を見ながら言葉を選び、接するようにしましょう。
4.宗教別|お悔やみの言葉のマナー
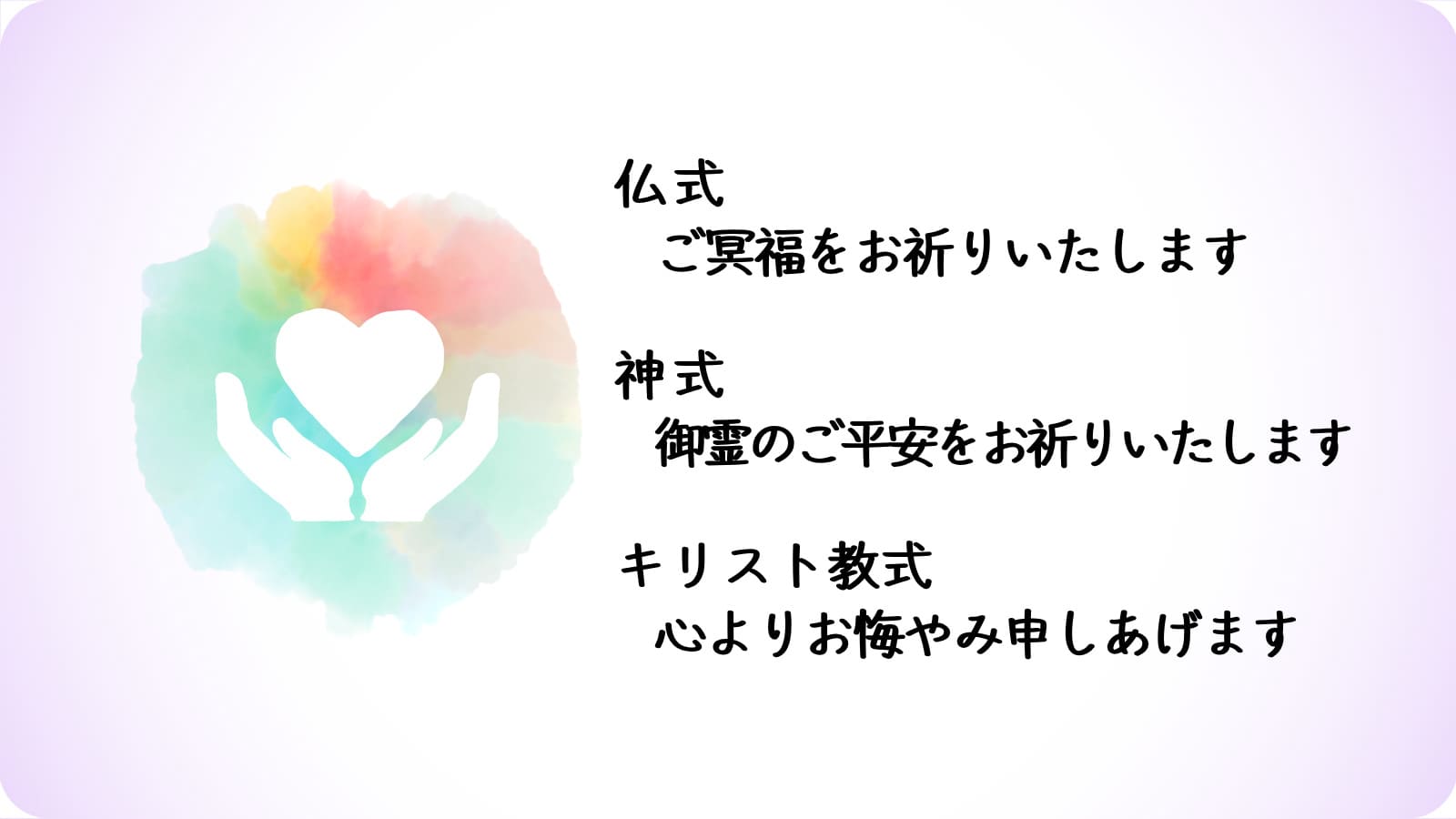
日本では、仏教、神道、キリスト教など、様々な宗教・宗派があります。お悔やみの言葉を伝える際も、それぞれの宗教・宗派に合わせた言葉遣いを心掛けることが大切です。ここでは、代表的な3つの宗教におけるお悔やみの言葉のマナーについて解説します。
仏式
仏式では以下の言葉が一般的です。
・「ご冥福をお祈りいたします」
故人が安らかに成仏できるよう祈る言葉です。
・「ご愁傷様です」
遺族の悲しみに寄り添う言葉です。
これらに加えて、
・「お念仏申し上げます」
・「ご仏前にお花を供えさせていただきました」
などもよく使われます。
神式
神式では「ご愁傷様です」は使いません。代わりに、
・「御霊のご平安をお祈りいたします」
・「御愁傷様です」
といった言葉を使います。
・「御霊のご平安をお祈りいたします」
故人の御霊(みたま)が安らかであるよう祈る言葉です。
・「御愁傷様です」
遺族の悲しみに寄り添う言葉です。
キリスト教式
キリスト教式では以下の言葉が一般的です。
・「ご愁傷様です」
遺族の悲しみに寄り添う言葉です。
・「心よりお悔やみ申し上げます」
遺族の悲しみに対するお悔やみの気持ちを伝える言葉です。
これらに加えて、
・「神様の平安がありますように」
・「安らかにお眠りください」
などもキリスト教式の葬儀でよく使われます。
その他の宗教・宗派
その他の宗教・宗派でも、それぞれに適切な言葉遣いがあります。事前に確認しておき、失礼のないようにしましょう。
宗教・宗派がわからない場合
宗教や宗派がわからない場合は、「ご愁傷様です」や「心よりお悔やみ申し上げます」といった、宗教・宗派を問わず使える言葉を選びましょう。
5.まとめ
葬儀後の遺族にかけたい言葉は、遺族の心に寄り添って支えになる言葉です。この記事では、シーン別・宗教別にふさわしい言葉遣いや、避けるべき表現を紹介しました。
大切なのは形式的な言葉ではなく、心からの気持ちで接することです。言葉が見つからなければ無理に探す必要はありません。そばにいて話を聞いたり、一緒に過ごすだけでも十分です。
悲しみはすぐに癒えるものではありませんが、あなたの温かい言葉や気持ちが、遺族の心を癒し、支える力となるはずです。


























